毎日が慌ただしく、「余裕がない」と感じていませんか?
仕事や家事に追われ、自分を見失いそうになる――そんな日々を変えたいと願うあなたへ。
私は、共働き家庭で子どもを育てる30代の男です。
毎日フルタイムで働きながら、自炊歴19年、読書は年間100冊を続けています。
かつては「時間が足りない」が口ぐせでしたが、育休をきっかけに考え方を見直し、読書と自炊によって心の余白を取り戻す生き方にたどり着きました。
この記事では、
- 忙しさは「やることの多さ」ではなく「思い込み」や「不安」から生まれていること
- 育休を経て気づいた、時間よりも「感覚」を取り戻すことの大切さ
- そして、読書と自炊がどう“心の余白”を育ててくれるか
についてお話しします。
「毎日忙しくてつらい」「心の余裕が欲しい」と感じる方に、
ほんの少し立ち止まって、暮らしを見つめ直すきっかけを届けられたら嬉しいです。
余裕がないのは「時間が足りない」だけじゃない
やることが多すぎるという「思い込み」
「やるべきことが山のようにある」
「全てが重要、とにかく完璧にやらなくては」
そう思って、1日を始めていませんか。
かつての私がそうでした。
まるで自らタスクの山を積み上げ、そこに埋もれるように、毎日を過ごしていました。
仕事も家事も完璧に、でも自分の時間もほしい。
そんなふうに“常に限界まで頑張ること=最善”と信じていました。
実は「やるべきこと」の中には、自分が勝手に「やるべきだ」と「思い込んでいるだけ」で、
「やらなくてもいいこと」が案外たくさんあります。
忙しさに絶望した時、自分に問いかけてみてください。
それは本当に「今やるべきこと」なのか? と。
全体像が見えないことからくる「不安」
必死に目の前のタスクを追いかけていると、
「何のためにやっているのか」が見えなくなることがあります。
例えば、
- 仕事の締切に追われているとき
- 家事のリストを片っ端から片付けているとき。
元々は何かの目的に向けた1工程だったはずなのに
目の前のタスクしか見えなくなってしまう。
先の見えない集中は不安を生み、いつしか
「とにかくやってないと怖い」「動いていないと落ち着かない」
そんな状態を作り出してしまいます。
自分はどこに向かっているのか、今どこにいるのか
抱えるタスクの全体像が分かれば、不安はおのずと消えていく。
「時間の無駄」なんて言わず、立ち止まって全体像を確かめてみましょう。
大切にされたいという「期待」
私たちの無意識は「苦労すれば周りから大切にしてもらえる」
と期待していることがあります。
子どものころ、
- けがや病気の時、みんなに優しくしてもらった
- 困難を乗り越えた主人公が周りから認められる物語を聞いた
こんな経験をした人も多いはず。
知らないうちに「苦労」と「大事にされること」を結び付けた無意識は
「みんなから大事にされること」を求めて
「苦労している、忙しい自分」を作ってしまいます。
次々とタスクが舞い込む
新たな問題が際限なく湧いてくる
そんな時必要なのは、「時間」ではなく「自分への優しさ」なのかもしれません。
育休がくれた「時間」ではなく「感覚」の変化
「余裕がないのは「時間が足りない」だけではない」という気づきは「読書」で得られたものですが、きっかけは3ヶ月間の育児休業でした。
今が永遠に続くという錯覚
育児休業を取る以前、私は忙しく働くことこそが正義だと信じていました。
- 毎日残業は当たり前。
- 休暇は甘え。
- とにかく頑張ることが正しい。
立ち止まって考えることもなく、
「このままでいいのか」という疑問すら感じない日々。
果ては出産にも立ち会わず、子どもは休日出勤中に生まれることに。
しかし育児休業を機に生活は一変し、
仕事中心の生活から子どもと妻を中心とした暮らしへ。
「忙しく働いていればいい」という「正義」は音を立てて崩れていきました。
慣れない育児で模索する日々の中、ふと気づいたのです。
私はずっと「今が永遠に続く」と思い込んでいました。
- 自分はずっと元気で自由に働く時間がある。
- 家族や世間はずっと変わらず安定している。
- 仕事を頑張ってさえいればいつか報われる。
そんな前提の中で、変わる努力をどこか避けていたのかもしれません。
でも実際は、何ひとつ、永遠には続かない。
育休という“強制的な日常の変化”によって、ようやくそれを実感したのです。
この気づきは、私にとってひとつの転機でした。
「変化する人生を、どう生きていけばいいのか」
そのヒントを求めて、私は読書を始めました。
小さな問いを抱えながら、自分の心に耳をすます時間が始まったのです。
人生における幸せの源泉
子どもができるまで、私は「幸せは頑張っていれば自然に手に入るもの」だと思っていました。
働いて、結婚して、家を持って──
いわゆる“世間の幸せの形”を追いかけていれば、それでいいと思っていたのです。
実際、給料日や、車を買った瞬間にはたしかに嬉しさがありました。
でもその高揚感は長くは続かず、気づけばまた忙しさの中に戻っていく。
「あれ、これって本当に幸せなんだっけ?」
そんな違和感が、ずっと心の片隅にありました。
そんな中はじめて経験した育休と子育て。
仕事ではなく生活や家族に向き合う中で
「忙しいながらも幸せ」という新たな感覚を経験しました。
- 育児の合間で静かにコーヒーを飲む時
- 家族と自分のために家事をしている時
- やっと眠った子どもの寝顔を見ている時
日常の中に「あ、幸せだ」と思える瞬間は、確かに存在していました。
その瞬間には、条件も結果も要らない。
「感じられる余白」こそが、幸せの源泉かもしれない。
そう思うようになってから、私は意識的に“心の余白”を探すようになりました。
「心の余白」をつくるためにできること
忙しさに追われる毎日でも、
少しずつなら、心の余白を取り戻すことができる。
私にとって、その手助けになった習慣が2つあります。
ひとつは「読書」、もうひとつは「自炊」です。
どちらも、手軽にできることではあるけれど、
忙しい日々の中で「わざわざ」やるのはむずかしい。
でも、だからこそ、大きな効果があると感じています。
「読書」で視野を広げる
頭の中だけで考えていると、答えのない悩みにぐるぐると迷い込んでしまうこともしばしば…
そんなとき、私にとって“抜け道”になってくれたのが、読書でした。
本の言葉は、著者が人生で得た学びや苦悩が凝縮・洗練されたもの。
誰かが悩んだり、乗り越えたりしてきた経験が、ページを通じて静かに届く。
それらの言葉は、単なる知識ではなく、
自分では気づけなかった視点や、思い込みを外してくれるヒントになります。
私は学生時代まったく本を読んでいませんでしたが、
今では読書が習慣になり、年間100冊ほど読んでいます。
読書は、言葉の形をした“他人の経験・答え”を借り、視野を広げること。
一人で抱え込んでいた時には見えなかったものが、ふと見えてくる感覚があります。
「自炊」で自分と向き合う
育休に入るまで、自炊はただの生活習慣のひとつでした。
必要だから毎日自然とやってきたこと――それ以上でも以下でもなかったのです。
しかし、時間の流れが変わった育休生活の中で、いつものようにキッチンに立っていると、ふと気がつきました。
「今日は何を作ろう?」
冷蔵庫やスーパーの売り場を見て、自分の食べたいものを思い出す。
「今あるもの」と「自分の望み」の差を見極め、それを埋めていく作業は、まるで自分自身と静かに会話しているようでした。
これまで当たり前にこなしていた料理が、
「自分に目を向ける」練習であり、
「自分の今と、理想との間を埋める」体験だったことに気づいたのです。
不安や忙しさの中でも唯一変わらなかったこの時間が、
「自分を保ち、立て直す」心の拠り所になっていました。
料理は、完成形を目指すというより、「今の自分と対話する」行為。
そのことに気づいてから、自炊は私にとっての“自分を知るための余白”へと変わりました。
おわりに―暮らしの中にひとさじの余白を
気づけば、いつも「時間が足りない」と感じていた日々。
でも実際には、足りなかったのは時間ではなく、「心の余白」だったのかもしれません。
忙しさに飲み込まれそうになるとき、
ほんの少しでも自分の心に向き合う時間があるだけで、見えるものが変わってくる。
その余白をくれたのが、私にとっては読書と自炊でした。
もちろん、すぐに人生が変わるわけではありません。
でも、小さな変化を積み重ねることで、
「自分の暮らしを、自分の手で整えていく感覚」が少しずつ育っていきます。
このブログでは、そんな感覚を大切にしながら、
忙しい毎日の中で心をほどくヒントや、
自炊・読書から得た気づきを少しずつ綴っていきます。
あなたの暮らしにも、ひとさじの余白が届きますように。
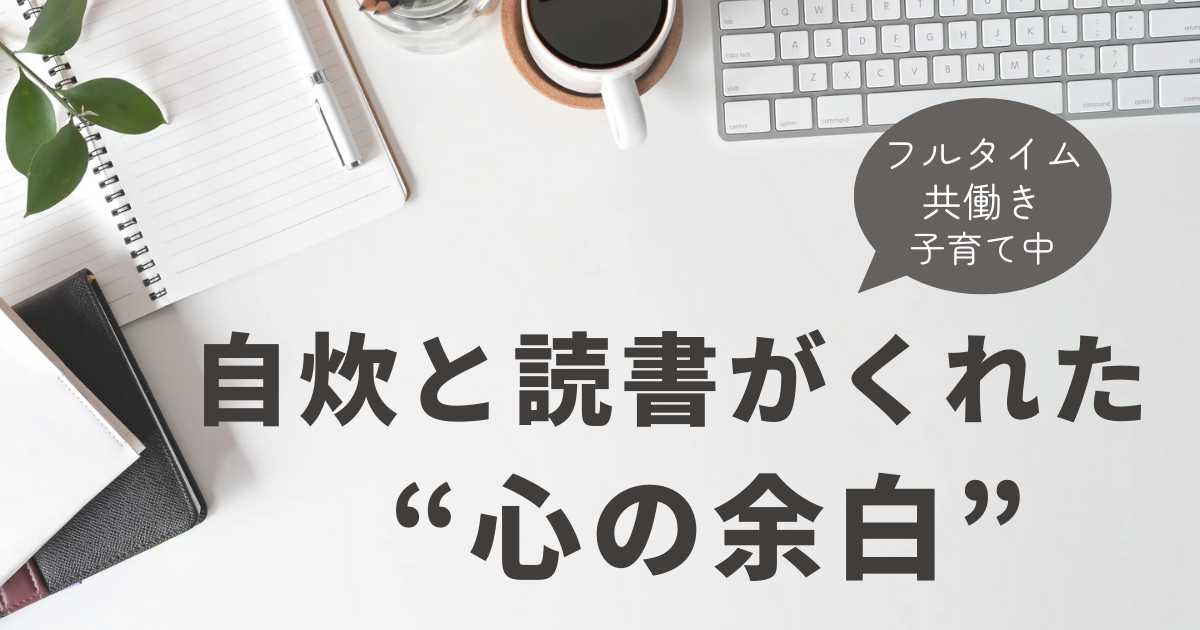
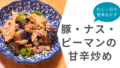
コメント