「時間がない」「やりたいことができない」「どうでもいいことに時間を使ってしまった」
いつもそんなふうに感じている人はいませんか?
そんな方に向けて、佐藤舞さんの書かれた“あっという間に人は死ぬから「時間を食べつくすモンスター」の正体と倒し方”という本をご紹介します。
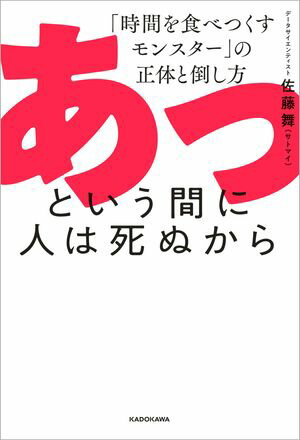
この記事では
について整理していきます。
読み終える頃にはきっと、「やりたいことに時間を使える自分」になるためのヒントをつかめるのではないでしょうか。
時間を浪費してしまう原因は代替行動
この本では時間を浪費する原因を「向き合いたくない真実からにげるため」と整理しています。
向き合わなければいけない本質から目をそらし、それでいいんだといいわけをすることに時間を使っている。これが、人生の浪費の正体
向き合いたくないことから逃れるため、代わりに行う行動を「代替行動」といいます。
実は私たちが無意識に行うことの多くが、この代替行動にあたると、本書は指摘しています。

確かに学生の頃、勉強しないといけないのに机の掃除やゲームをしたり、今も将来やお金のことについて考えなきゃと思いながらSNSしちゃってるなあ…

そう、まさにその掃除やゲーム、SNSが代替行動なんです。
これは、どれだけやっても本当の解決につながらないから、満足感が得られずについやりすぎてしまう。
また、SNSやギャンブルのように脳内物質のドーパミンを放出させて快楽を感じるものは特に強力。
「どれだけやっても満たされない」という代替行動の特徴とドーパミンが合わさることで、依存や中毒の原因になることも。
「死・孤独・責任と向き合う」というシンプルな対策

代替行動をやめるにはどうすればいいの?

人が普段避けている真実、「死・孤独・責任」と向き合うことが対策になります。
本書では「死・孤独・責任」を「人生の3つの理(ことわり)」と位置づけ、私たちが直視できずにいることで、不安をもたらし、代替行動を生じさせる原因として取り上げています。
死、孤独、責任には、不安が伴います。目に見えるものではないので、底知れぬ「漠然とした不安」として、心理的な苦痛(ストレス)が生じ、この不安を何かで紛らわそうとします。
そしてこれら3つに向き合うことが、代替行動を止め、人生の浪費を食い止める対策になります。

ほかの本では「本質」とか「自分が大事だと思うこと」といった漠然とした表現のこともありますが、この本では「死・孤独・責任」の3つと明確に書かれていて、わかりやすいのが特徴的ですね。
人生には「苦」が必要
「死・孤独・責任」への向き合い方として、本書では3つの原則が紹介されています。そのうちの一つが「人生には苦が必要である」です。

ええ?「苦」なんて無い方がいいに決まってるでしょ?なるべく苦しみの少ない楽な人生にしたいよー

そうですね。幸せになるには、ポジティブを増やして、ネガティブを減らすことが必要じゃないかって思うし、実際世間にはそんな主張や宣伝が溢れています。でも実は「苦」も幸せに必要な要素なんです。
「苦」を避けることが目的になる
人には「○○について考えるな」と言われると、逆にその○○について考えてしまうという性質があります。
これは「シロクマ問題」(「シロクマのことを考えてください」と言われるよりも、「シロクマのことを考えないでください」と言われる方が、シロクマについて考えてしまう)と呼ばれ、日常でもよく見られる現象です。
ただこの性質があることによって、「苦」を避けようとすると、かえってそればかりが気になり、「苦」から逃げることで頭が一杯になってしまいます。
自分が大切にしたいものではなく、自分にとって嫌なものに焦点が当たってしまうと、「嫌なもの」から逃げよう、無くそうとすることに時間が使われ、底なし沼にハマってしまいます

なるほど。僕も毎日上司に怒られたくない、残業したくないって思いながら、怒られる場面を想像したり、気を紛らわそうとしてお菓子を食べたりしてるよ…

私も仕事を忙しくすることで、「苦」から逃げようとすることがあります。
でもこれはまさに「代替行動」なので、どこまでやっても終わりがないんです。
不安やストレスといった「苦」を避けよう、取り除こうとすればするほど、「苦」のことばかり考えてしまう。
そして増幅された「苦」から逃れるため、代替行動に時間を費やすものの、その間に解決されない「苦」がますます増えていく…
こんな無限のループに心当たりはないでしょうか。
人生における「苦」を「あるのが普通」と向き合い、受け入れることが、実は生きやすさにつながります。
感情と出来事を切り離し、「価値観」で考える

でもさ、「苦」なんてそれこそ無限にあるよ?
僕なんて朝起きるのも嫌だし、満員電車はストレスだし、上司は怖いし。
全部を受け入れて対応するなんて無理じゃないの?

実は「苦」について考えるときは、感情と出来事を切り離して考えることが大事なんです。
人の脳は、不安や焦り、不快といった感情の発生によって「苦」を認識し、避けようとします。
しかし感情は自分の意思に関係なく自動で発生する「制御できないもの」。
そのため「不安や不快になった=自分にとって悪い出来事が起きた」ということではありません。
例えば、なにか新しいことに挑戦する時。
初めて経験することは不安やストレスを感じるものですが、それだけで「自分には向いていない」とか「挑戦すべきでない」とは判断できません。
感情とその出来事が持つ自分にとっての価値・意味は一致しないのです。
「ストレスがかかること=自分が本当にやりたいことではない」という認知のゆがみから、飛躍した結論を出して、自分を正当化していないでしょうか

うっ、確かに。自分のためになることでも疲れたり、面倒なことはあるもんね。
でもじゃあどうやって判断すればいいの?
中には本当にやるべきじゃないものもあるでしょ?

そこで判断の基準になるのが「価値観」です。実はここが、この本で私が一番ハッとしたところなんです。
価値観とは、どうありたいか、何を大切に生きるのかという「方向性」のことです。
・その時点で最善の選択を考えて実行できる、自由な状態を増やしたい
・家族や友人とのつながりから幸せを感じ、自己理解を深めたい
価値観は感情と異なり、自分で考えて設定するもの。これを判断の基準にすることで、人生の方向性が定まり、感情に振り回されにくくなります。
例えば、「家族や友人とのつながりから幸せを感じ、自己理解を深めたい」という価値観を持っている場合。
家族のために家事をしたり、友人との食事を企画するのは、感情的には「面倒」かもしれません。
しかしこれらの行動は、価値観に沿っており、自分の幸せに繋がるため、「やった方がいい」と判断できます。
逆に、家族や友人との時間をとらずに一人でダラダラ過ごすことは、感情的には「ラク」かもしれませんが、自分の幸せには繋がりにくく、「やらない方がいい」と判断できます。

なるほどー。価値観に沿わず、感情だけに従って「苦」を避けた結果がさっきの「代替行動」なんだね。
…僕の日常は代替行動だらけだよ、そりゃ幸せになれないわけだ。

もちろん、感情も無視するんじゃなくて「自分はこう感じているんだな」と受け止めてあげることは大事です。
でも「不快感=悪」とは限らないし、感情的な「苦」の先に自分の幸せがあるかもしれないことも忘れずに。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した本書での学びは次の通り
- 時間を浪費してしまう原因は「向き合いたくない真実からにげるため」の代替行動
- 対策は普段人が避けている3つの原則「死・孤独・責任」と向き合うこと
- 「苦」は幸せな人生に必要な要素であること
便利なはずの現代にまん延する「時間がない」という悩み。
これにひとつの明確な結論を示す本書は、多忙な現役・子育て世代の多くの方に役立つものだと思います。
また、多くの自己啓発書で「嫌なことはしなくてもいい」「直観に従おう」といったアドバイスがある中、「苦は人生に必要」という主張は斬新かもしれません。
しかし、頑張って困難を乗り越え、幸福感を得た経験のある方にとっては、ぼんやりした感覚が整理されたような、スッキリ感のある考えではないでしょうか。

本書ではほかにも、現代人が幸せを感じられない原因から、価値観の作り方や活かし方といった具体的な解決策まで、幸せに生きるためのヒントが盛りだくさんです。
「時間がないことに悩んでいる」、「自分の行動を変えるヒントが欲しい」という方にはぴったりの本だと思いますので、興味のある方はぜひ読んでみてくださいね。
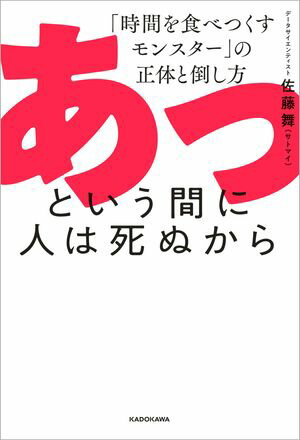
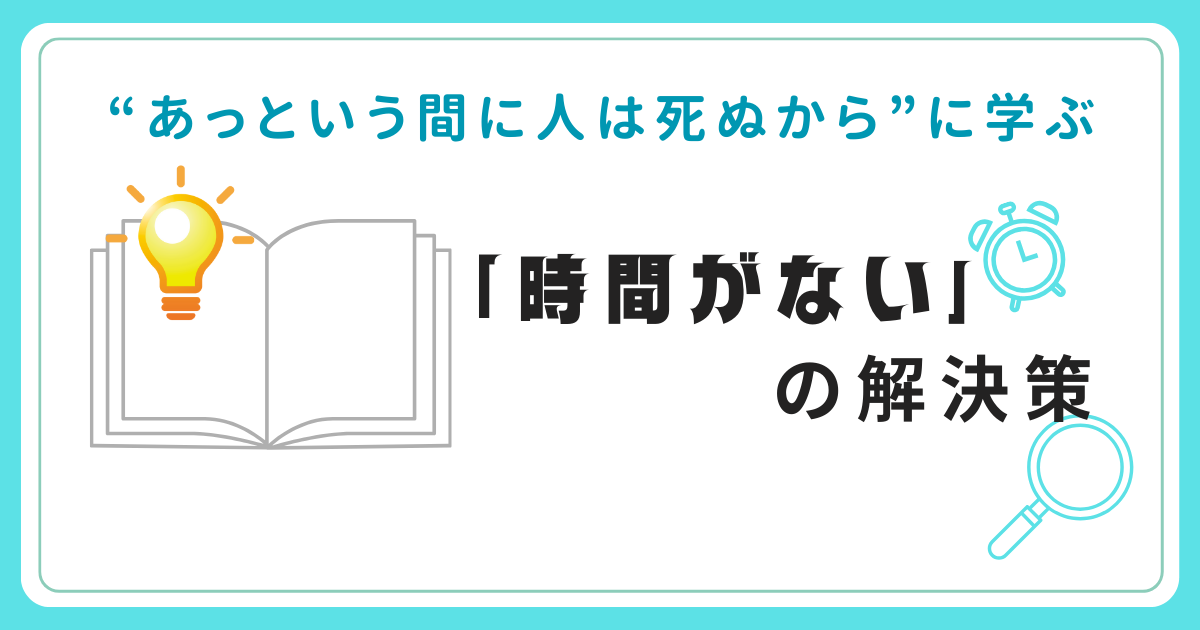
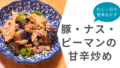
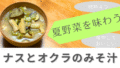
コメント